エメラルドの百足と姫君と花火師の話
百足が姫に恋をした。彼は山を七度巻くほど長く、巨大で、強かった。
姫が生まれたときに、占い師が告げた。この姫には不吉があるだろうと占った。
二親は悲しんだ。不吉がある姫を都にはおけない。かといって、殺すこともできない。僻地に移して、祈るしかなかった。
物心ついたときから姫君は一人高い塔に住んだ。時折の手紙のやり取りと、窓から外を見下ろすことだけを楽しみにしていた。
月の夜、長い髪をたなびかせ、窓から外を見下ろす姫に百足は心を奪われた。彼の目は三日歩いた先に落ちた針まで見通せた。
けれど百足の姿では恐れられるだけだろうと、彼は地の果てまで旅をした。雲海の上にある社には、鬼に守られた三つ目の巫女がいるという。金の三つ目を持つ巫女は会うものの願いを叶えるとも百足は聞いた。
果たして彼は足の半分を失い、毒の体液を垂らしながら社の前までたどり着いた。石まみれの山に、赤い鳥居が立っていた。その参道前で彼は待った。自分の毒で巫女や鬼に害を与えてはならぬと思ったからである。七度太陽が落ちたあと、一人の男が鳥居から出てきた。美しい男で、額に短く薄い翡翠色の角が生えていた。袴を穿いた鬼の男は、白銀の太刀を持っていたから従者とわかった。男は鳥居の中から百足へ話しかけた。
「ここでなにをしている」
「巫女様に願いがあって罷り越しました」
「さようか。けれど願いはただでは叶わぬ。お前の大事なものと引き換えになる。子を助けに来て己に子がいることを忘れ果てた女がいた。妹を助けに来て妻を犠牲にした男もいる。
総じて、前より幸せになったものはおらぬ。
それでもお前は望むか。おそらく、望むであろうが」
男の横顔は苦かった。
百足はもちろん、それでも、と望んだ。希望を持つことを止めるのは死ぬようなものだからだ。このまま姫の前に出られない身であるより、一目でも会って話してみたかった。そして百足は金色の三つ目を持った巫女に謁見できた。金色の髪を尼そぎにして緋袴をはいていた。
「お前はとても醜いけれど」
巫女は微笑んだ。「分をわきまえて鳥居の前で待っていたから気に入ったわ。お前の願いを言ってご覧。聞き届けてあげよう」
百足は答えた。
「この醜い姿を美しくして下されば、あの姫が自分を恐れず喜んでくれたら、それが自分の願いです」
「聞き届けましょう。とても、とても美しくしてあげる。誰もがお前を欲しがるような、そんな姿にしてあげる」
鈴を振るような声だった。百足は耳がしびれるような気がした。しびれは全身に広がって、あっと思ったときには気を失っていた。
百足は目を開いた。いつもの、湿った土の匂いがする自分のねぐらの中だった。夢をみていたようだった。這い出して、水を飲もうと池に近づいた。水面に映る姿は変わっていた。
巫女は確かに願いを叶えた。
獰猛な顎も、数多い足も、末端の尾も、全てエメラルドに変わっていた。太陽に美しく輝き、透き通った光は緑の影をつくる。這うたびに恐ろしげな音を出した胴も楽器のような響きを立てた。
それでも、形は百足のままだった。そっくりそのまま百足の心と身体のまま、素材だけがエメラルドになった。とても美しく、誰もが百足を欲しがる姿だった。
百足は嘆き苦しんだ。たとえこの身が宝石だろうと、数多の足を持ち毒の顎をもつ自分を恐れないものがいるはずがない。まして彼は山に七回巻きつけるほど巨大であったのだから。エメラルドの足を蠢かしても、誰が近寄ってくるはずもない。誰に嘆きを打ち明けられるはずもない。彼は絶望し、そして決めた。
それなら自分が姫を守ろう。たとえ一度も会えなくても、話すことさえできなくても。この強い体なら、弓も矢も槍も毒も効くはずがない。あの遠い塔で一人住まう姫に災い害なすものなど近づけさせることはしないと、彼はそう決めた。
雲海の果てに住む鬼が噂を聞いたのは、しばらくあとだ。
高い塔に住み、不吉から逃れ続けていた姫についに災いが現れたという話だった。その話をした商人は石に腰掛け、煙管を吹かしながら鬼に話した。
「エメラルドで出来たでっかい百足がやってきて、誰も姫君に近づかせやしないんだそうですよ。宝石と姫を求めて、数多の男が挑んだが誰一人帰ってきやしない。ここにくるやつも、そろそろいるんじゃないですかねえ」
鬼は悲しんだ。希望を叶えるといいながら、はぐらかし続ける今の巫女は人の望みを食って生きている。希望はなにより強い力で、すべてが生きる限り必要とするものだからだ。先代はそうでなかったし、次代もおそらくそうではない。人の望みを叶えながら、ささやかな分け前をもらうのが本来の有り様だった。けれど今の巫女は強くなりすぎて、鬼は警告することしかできなくなってしまった。
エメラルドの百足は敵をほふり続けた。彼の宝石の身体と、美しい姫を狙う輩は途切れることはなかった。
ある夜のことだった。百足が塔に巻き付いていると、月のない空に花火が打ち上がった。七色の光が夜をきらめかせた。塔の中から笑い声が聞こえてきた。
姫君が笑っている!
それは百足の初めて聞いた姫の笑い声だった。叶うなら彼は塔を食い破って、その笑顔を見てみたかった。それが出来たならこんなエメラルドの身体なんていくら打ち砕かれても構わなかった。彼は長い夜の中幾度か姫に会うことを考えてみないことはなかった。エメラルドの身体なら褒めてもらえるかもしれないと思わないではなかった。けれど彼は姫が自分の姿に怯えられでもしたらと考えただけで死ぬより辛かった。夜は花火に彩られ、月が出るまで続いた。
百足は太陽を食ってしまいたいほどだった。花火が出ている間、姫が笑っているからだ。朝になれば花火は色失せて、姫もまた黙ってしまう。
花火を打ち上げていたのは破門された見習いの花火師だった。未熟なときに失敗して顔が半分焼けただれ、自分には花火しか無いと打ち込んだ末に師匠より腕を上げすぎて、袋だたきにされた挙げ句に追い出された。思い上がった男だったので、頭を下げずに飛び出して、どこにも居所がなくなってしまった。火傷痕のせいだと男はふてくされた。そんな時、塔に住む姫と百足の話を彼は聞いた。
気の毒な話だと花火師は思った。その姫は百足に囚われたまま、何を見ることもなく朽ち果てていくのだろう。それは自分のようにも思えた。彼は山を越え、百足から逃げられるぎりぎりの場所で夜を待った。月のない夜に、花火は打ち上がった。
??花火よ、咲け。咲いて、彼女の気持ちを慰めろ。誰に見られることもなく、朽ち果てていく姿なら、一瞬の花火と変わりはしない。
花火師は次々と空に花を咲かせた。誰に顧みられることのない閃光の花が、夜に狂い咲いた。その花を見たのは姫と百足だけだった。翌日、塔から白い狼煙が上がった。
行き先のなかった花火師は夜が来るたび次々と花火を打ち上げた。花火が上がるあとの朝には、白い狼煙が細く上がった。
上げる花火は白、赤、青、金、手持ちの火薬を使い果たせば山にこもって掘り出した。流星のように、昇竜のように、形を変え色を変え技を尽くして打ち上げた。昼に花火は目立たない。彼は街に行き花の種を買った。昼間にも花が見えるように。
花火師を傍らに戦士が何人も通り過ぎて死体になっていった。彼らのいくたりかは花火師に尋ねたこともある。どうしてお前はこんなところで花火を上げているのかと。
「だって気の毒でしょう。まだ若いのに、花の一つも見ないでいるなんて」
彼は自分の言葉がある意味で皮肉なことに気づいていなかった。彼は彼女の顔さえ見たことがない。かつての姫さえ花は愛でた。今は空に咲く花だけ仰ぎ見る。
花火の噂は遠くまで聞こえ、やがて百足とは逆の方向から見物する人々も出てきた。おかげで花火師の懐も暖かくなり、違う街で花火を打ち上げてくれと頼まれるようになった。
花火師は喜ぶはずだった。誰もが自分の花火を認め、讃えるのを夢見ていたはずだった。なのにさっぱり行く気がおきなかった。自分が去ってしまったら、誰が彼女のために花火を打ち上げるのか。か細い狼煙を上げる人は、暗い夜空に何を思うのか。そればかりが気になって、胸の鼓動が早くなる。
姫は幾度も死のうと思った。
生まれたときの占いで閉じ込められるのは腹が立つ。けれどいつかはウソだと笑って話せる日が来ると信じていた。小さいときは世話係がいたけれど、十二の年からは塔の天井にある小さな花畑と、鳩小屋の手入れだけして過ごした。小さな愛らしい鳩は手紙を運んでくれる。
一年に一度、黒い服を着た人々が必要な荷物を運び入れてくれる。言葉はない。姫は屋上で花に水をやって彼らが居なくなるのを待ち、終わってから荷物を開く。珊瑚の鏡台、紫檀の文箱、螺鈿の簪。彼女を慰めるために詰め込まれたものの中から、麻袋に入った種を取り出す。金盞花、鳳仙花、桔梗、女郎花、夕顔、朝顔、育てやすい品種の種を姫は出し、さてどう植えようか考える。ガラスの瓶に水を入れ、種を浸して芽吹きに備える。
朝起きれば地下の井戸から水を汲み上げ、屋上の花に水をやる。鳩に餌をやり、そして自分の身仕舞いをする。手紙を幾度も読み直し、遠い都や親のことを考える。
一月に一度手紙を書いて鳩に運んでもらう。その鳩が途切れがちになったのが発端だった。
やってきたのは話を聞けばエメラルドの百足らしくて、その化物は自分を助けようとしてくれた人々を殺し尽くした。
申し訳なくて死ぬしかなかった。母の形見の短剣を取り出して、刃を払った時気がついた。果たして自分が死んだ後、あの百足はどうするのか。暴れるのか、怒るのか。姫は死ぬのを諦めた。自分がこうして塔にいれば、少なくとも百足はここにいるようだ。百足がどうして自分を襲わないのか知らないが、他の地方で暴れられるより自分ひとりが犠牲になるほうがマシだろう。ただ死ぬのが怖くてそんな言い訳をしているのかもしれないと、姫は考えたが、死ぬなら少しは役に立って死にたかった。
とはいうものの、塔に閉じ込められてしまっては連絡をとる手段もなかった。たくさんの戦士たちがやってきては死体になっていた。おそらく百足がそれを食べていたのだが、なぜか自分が昼間、外に出ようとすると姿を見せない百足は尾で風を起こしてくるので止めようもなかった。木や岩の壊れる音で百足が苛立つのがわかった。昼間は窓の外へ顔をだすことも出来ず、部屋の中から眺めているしかできなかった。
誰も助けにきてほしくなかった。自分のために人が死ぬのはもう嫌だった。姫はいつも死ぬことばかり考えていた。そもそも蓄えが三年くらいしかなかったし、何れ朽ち果てるしかなかった。
蓄えを取り出すたびに、ああいっそ死ぬほうがと思うのが姫の日常だった。あるいは、姿を見せない百足に一矢報いることも考えた。塔に火を放てば少しは百足も苦しむかもしれない。
花火が打ち上がったのは閉じ込められて半年経った後だった。
もう周りは荒野に成り果てて、三ヶ月ほどは降るように来ていた戦士たちも途絶えた。月もない夜に轟音が響き、姫は驚いて外を見た。
昏い夜を切り裂いて咲く花は光で出来ていた。一つ、また一つ。自分はここにいるのだというように、花火は誇り高くほころんで散っていった。
??死ぬのならあれほどに潔く。
頬に涙が伝うのがわかった。花火でさえ散り際を知るのに、自分ときたら意地汚く生きている。自分が情けなくて、みじめで、おかしくて、笑いが出た。
姫は笑うしか出来なかった。
翌朝、塔の天井をわずかに壊して狼煙を立てた。誰が打ち上げたのか知らなかったが、自分は花火を見たのだと知らせたかった。たとえ誰が見ていなくても、自分はあの花火を美しいと思った。次の夜、また花火は上がった。
おそらくは自分のために花火をあげようとする人がいる。
姫はもう死のうとは思えなくなった。自分のために死んでしまった人、自分のために花火を上げてくれる人が居た。どうやっていいかわからないが、その人達に報いるまでは無責任に生から逃げることはできなかった。
食料が尽きるから姫の命も終わるだろうと花火師が聞いたのは秋のことだった。
教えてくれたのは彼の花火を楽しみにしている老人で、なにくれとなくいろいろなものを届けにきてくれていた。
「そろそろ逃げないと、怒り狂った百足がなにをするかわからないよ。儂はあんたの花火が好きだし、よかったら一緒に他の街へ行こうじゃないか」
「......蓄えが尽きるのは、どれくらいだ」
「さあ、噂では、三年持てばいいほうだと言われてたがねえ。もうまずいだろう。あの宝石でできた百足が来たときには、倒せば一攫千金だと思ったが、とんでもない災厄になってくれたもんだよ」
「ありがとう。もう少し考えるよ」
「そうかい。儂はあと十日で逃げるよ。下の街にいるから逃げといでよ」
老人の後ろ姿を見送った。花火師は腕を組んだ。風は冷たく、澄み切った空気は花火を美しく冴えさせるだろうと思えた。
自分は随分バカなことをしていると花火師はわかっていた。おとなしく違う街にいけば、名声も富も手に入るだろう。それなのに、こんなところで死ぬ覚悟を決めている。
ただ一度、一度きり、会って話ができたらいい。いや、一度でも見られたらそれでいい。自分の花火は彼女のためにあったのだから。
かつて師に逆らった時、自分は誰かのために花火を作ろうなどと考えただろうか。誰かに認められたい、褒められたい、自分の腕を見せびらかして自慢したい、それだけではなかったか。どこの街に行っても受け入れられず、喧嘩ばかりして他人は自分の醜い火傷痕ばかり見て批判し理解する者がいないなどとほざき、最初に花火を上げたときさえ自分の腕なら慰みになろうと思い上がってばかりだった。
いつの間にか変わっていた。どんな花火がいいだろう、白か、金か、赤か、青か。花なら桜か、菊か、朝顔か。あの人はどんな花火を喜ぶだろう。いつしか自我は消え失せた。ただ、相手のことだけが頭にあって、ひたすら突っ走った。
きっと喜んでいるだろう手応えはある。朝に上げられる狼煙でわかる。
だからこれで終わりだなどと見捨てて自分一人が去ることは、花火師には出来なかった。吐き気がするほどの恐怖がこみ上げても、彼は耐えた。
その夜の花火は絢爛の幕を開く。
仕掛け花火が上がる。上がれ、上がれ。花火師は胸の中で叫ぶ。これが最後の花火だ。百足の注意をそらすために、特製の花火も上げた。火のない花火だが、弾ける。中からは銀の小片が幾千万と降り注いだ。
百足が頭をもちあげた。見たこともない花火にいぶかり、塔の上まで頭を届かせた。花火が打ち上がる。白の閃光は荒野に、銀の小片に降り注ぐ。エメラルドの百足の身体を光は突き抜け、銀に反射する。風が吹きすさぶ草原が、刹那、荒野に幻出した。緑の光が乱舞する、かつてそこに在った野原の姿をとりもどすかのように。百足は大地を見下ろした。次の花火が上がる。二発。
轟音の花火と、光の花火。時間差で上がる花火に、百足は頭を伸ばした。その上で光が開く。紅蓮の花が光となって降り注ぐ。彼岸花だった。緑の百足を茎に見立てて、その上で花火師は花を咲かせた。弔いの花のつもりだった。その光景に姫は息を呑んだ。恐ろしいはずなのに、初めて光の下で見た百足に目を奪われた。エメラルドの胴体を貫いた光が、姫の白い顔を緑に彩った。
??ああ、なんて、美しい......。
同じように百足は見惚れていた。身体を這う感覚に我を取り戻す。忌々しい敵が、必死になって自分を越えようとしていた。彼は身体をのたうたせ、叩き潰そうとのけぞった。花火師は手にした花火を投げつけようと振りかぶる。手筒花火が姫の目に入った。彼女は身体を乗り出して、恐怖で言えなかった言葉を叫んだ。
「帰って下さい!」
声が響いた。終わりの仕掛け花火が花開いて、その顔を白く輝かせた。「引き返して下さい!お願い、そうでないと、あなたが死んでしまうから!」
姫君は花火師を見ていた。
花火師も姫君を見ていた。
百足はそれを見ていた。恐怖で身体がこわばるのがわかった。見えてしまった、この恐ろしい姿を彼女はどう思うだろう。
最初はただ一度、会ってみたかった。話してみたかった。一回でいいから、姫の顔を見てみたかった。それがかなわないなら、姫の敵など打ち砕いて、殺して、滅ぼして、どんなことでもやってきた。姫は自分を怖がるだろうから、姿は隠したまま、痛いのも苦しいのも我慢して我慢して、ずっと戦ってきた。脳裏に、金色の三つ目を持つ巫女が現れた。紅唇を彼女は歪ませる。
??愚かな子。姫はお前のことなんか、目もくれていなかった。ほらご覧。彼女が見るのはお前じゃない。
お前が、姫の災いなのよ。誰にも会わせず、誰にも触れさせず、彼女に関わるものたちをすべて喰らい尽くしたお前こそ、姫の敵。
頭上に散る光の花とともに、百足は自分の心臓が凍りついてヒビが入るのがわかった。蜘蛛の巣のように白く身体に走ったひび割れはまたたく間に広がる。頭が潰れ、足が外れ、毒液を垂らす顎牙が落ちていく。砕けてしまえ。百足は思った。自分のことなど彼女は目にもくれていないのだから。
エメラルドの百足は粉々に崩れて、大地に跳ね返った。その姿さえ、生き残った二人は見ていなかった。
かつて、と、この土地の古老はいう。
??巨大な百足に呪われた姫がいたそうな。幾千万の兵も、一騎当千の戦士も百足を倒せなかったが、孤独な姫を哀れんだ花火師が上げた花火に百足は倒されて、宝石の山となったそうな。生き残った二人は宝石を殺された人たちを弔うことと生き残った人たちのために使って、皆、幸せになったそうな。めでたし、めでたし、と。
雲海の果てにある巫女の館で、鬼が平伏していた。捧げるはエメラルドの破片、巫女に命じられて持ち帰ってきた。巫女は百足の足の姿をした宝石を手にして、それに優しく口づけた。
「おかえりなさい、愚かな子。お前はこう願えばよかったの。
『姫君が望む姿にして下さい』と。
お前は相手がどう思うか考えず、ひたすら暴れて自分の気持ちを押し付けた。あんなにきれいな身体をあげたのに、バカな上に臆病で、姫に否定されることばかり怖がって逃げ回ってばかりいた。
たったひとこと、話しかけてみたらよかったのにね?
姫はお前を美しいと思ったのだから。
ああ、でも、あの花火師のおかげかもしれないわね?あんなきれいな花火は初めてみたもの。まるで飛ばされた生首みたいに赤い花」
鈴を転がす笑い声が響く。巫女は笑いを止めた。平服する鬼の頭を踏む。
「安心なさいな。知ってるでしょう、私は自分で願いを叶えたものには手出しはできない。あの二人は何も知らず幸せに生きていくでしょう。時折自分のために死んだもののために良心を傷めるけど、あれだけ宝石があれば償いは十分できるもの。
だから話はここでおしまい。めでたし、めでたし」
からりと宝石が投げ捨てられた。
巫女は退出する。また、願いを叶えてもらいに来た犠牲者に会いに行くのだろう。鬼は吐息をついた。あの巫女はまだ殺せない。力が足りてはいない。
参道を降りて、鳥居の外に出る。鬼は百足の来た方角につぶやいた。
「......百足よ。
お前は愚かで最後まで身勝手だったけれど、お前のことは俺が覚えていよう。私にはそれしかできないが、許せとは言わぬ。
忘れないよ、お前が姫を愛したことは」
かつて百足が姫に恋をした。はじめはただそれだけで、おわりもただそれだけだった。
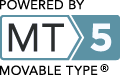
コメントする